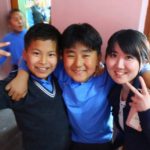北海道大学歯学部 豊福明日香
「生きる」とはなんなのだろう。なぜ「生きる」ことに意味を見出そうとするのだろう。自分をここまで「生かし」続けさせたものとはなんなのだろう。チベット亡命政府の元を訪れ、亡命してきたというチベットの学生と話し、またスラムを含めたインドのさまざまな場所と出会いそこに居る人々と出会う中で、どうしてもこれらの問いに向き合わざるを得なくなった。日本で何一つ不自由のない暮らしを送る一介の学生に、これだけ「生」のリアルさというものを痛感させ、かつその常識や当たり前に疑問を投げかけるほどに、インドという国はあまりに多様でカラフルで、チベットという「国」の人々はあまりに特別で、もし人間のイデアというものが存在するならイデアに近い人間のようにもみえた。
尤も、彼らには、彼らの在り方が当たり前であって特別だとかそのような意識がほぼ無いことは承知しているのだが。
ここでは、あくまで私が見たのはほんの一面に過ぎないことを念頭に置きながらもチベット社会そしてインド社会から、「生きる」姿というものをつらつらと書きだしてみる。

チベット人が生きる糧としているものは輪廻転生をもとにした宗教観と非常に優れた宗教的指導者であるダライラマの存在という精神的支柱であり、生き続けるという意志と自分の存在を支えているものに、あらゆる命が身近にあり、その命の中で自分がつながり生きるという生のリアルさ、インド社会の多様性と寛容性があると思う。
まずそのなかのひとつ、生のリアリティとはなんなのか。私が今考えているものとしては、今の自分を成り立たせてきたもの・人・場所などあらゆるものへの自覚的な実感である。例えば、ダラムサラで生きるチベットの人には、自分の命があるのは他の生きとし生けるものをいただいているからであり、地球と一つの生き物としての自分、命のつながりへの圧倒的な認識があると思う。道で野菜を売るおじちゃんの斜め向かいでは、鶏の首を落とし羽をむしりその肉を切り売りする人がいる。その鶏の羽毛が物凄い勢いでもうもうと舞い散る中、一方では魚をそのままの姿で並べて売るお兄さんがいる。小さい子供から大人まで、自分が何を食べているのか即ち何によって自分の命がつながれているのか身体の感覚として解っていて、だからこそ生きることが生きることとして輝いているようにも感じた。
また、家族や隣人との濃い結びつきや場所としての土地、家、地域社会は、自分を構成する大切な一ピースでもあり自分がそこに存在すべき役割でもあり安心できる居場所でもあり、なによりそれは自分を確かめる輪郭でもあるのかもしれない。地球という球体のほんの一部の点であるインドのダラムサラという場所で、当たり前のように誰か大切な人がそこにいて必要とし必要とされる、勿論凄惨な歴史によってそれがもう今では叶わないチベットの人も本当に多いけれど、だからこそ、そのひとの一人ひとりの存在の有難味と感謝を染み入るように心の奥で掴んでいるようだ。
逆説的であるようだが、生のリアリティというものを抱えながらも、確固たるアイデンティティを持ち誰にも揺るがされないような自分の強い信念を軸にしながらも、チベット仏教の輪廻転生を基にした価値観・世界観により、彼らはこの世界の何かに固執するということがないようにもみえ、淡々となすべきことをし、生きるということを全うしている。幸福や平和といったものが自分の内なる穏やかであたたかな泉源によって実現しうるものであるとか、今この瞬間の次に自分がここにいるなんて保障も確証もないという、私には到底想定もつかなかった感覚を持って毎日に臨んでいる人もいた。固執がないからこそこれまで存在し今存在するものに対して愛があり慈しみがある、とも言えるのかもしれない。またそんな彼らチベットの友人を受け入れるだけのインド社会の多様性と寛容性が、彼らがここで生きる支えとなっているようにも思う。宗教という観点から見ても、インドのコミュニティは自分と異質なものを排除する精神はなくむしろそれを包み込むものが多いという。例えば村のほとんどがクリスチャンでたった3家族だけがムスリムだったとしても、決して少数派の人が恐怖に怯えることはないとダライラマも言っている。人種も宗教もあらゆる違いがそこにあるだけという多様性のあり方、清濁伏せのむカルチャーと環境は、きっとそこに生きる人々の心を癒している。

ここで冒頭の問に戻ってみたい。私が「生きる」という行為を、息を吸うように当たり前に自然なものとして漠然と考えていたのには、自分が生を脅かされない環境で何かを欠くこともなく豊かさの恩恵に浸りきっていたから、ゆえに世界の生生しさにも目を逸らしていたから。一方で同じ「生きる」という行為を、独自の宗教的世界観で意味づけしながらも、圧倒的にその日常が非日常の刹那さを帯び、まわりを慈しみ過ごす人がそこにはいた。自分を生かし続けるものに対して自覚的であるのが後者で、自覚にいたらないのが前者である。そしてきっと生きる自分の存在意義なんてものは、どんな宗教かに関わらず、それがどんなに大切でも大切でなくても、知性である人間が意味づけした世界の中でしか存在しないのだと思う。それでもどうしてもきっと人間は自分の存在そのものを確かめたくて、人と世界とあたたかく繋がりたくて、意味を探し求めるのだろう。
ただ地球上の他でもない“この場所”に“人間として”生まれてきた。それが生きるということをシンプルにも、途轍もなく複雑にもしている。インドで出会ったチベットの人びとを見て改めてそう思った。私も生きることから逃げずに生きたい。